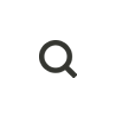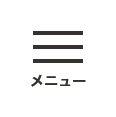協会の活動
関西医薬品協会の活動
Ⅱ 委員会・研究会活動に関する事項
1.薬事法規研究委員会
薬事法規研究委員会では、医薬品医療機器等法の法令遵守を推進していくと共に、法令、許認可、広告・プロモーション、包装・表示、一般薬、海外薬事などの分野ごとに部会を設置し、薬事法規に関する制度及び実務的な課題を中心に検討している。また、上部団体である日薬連薬制委員会のプロジェクト等へ積極的に参画し、薬事法規に関する課題への対応を行う。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- 薬事制度に関する調査・研究及び提言
医薬品医療機器等法における実務上の問題点を解決するために、会員会社から意見・要望を収集し、業務上の諸問題について調査、研究を行い、実際の運用に反映すべきものは通知等で対応していただくよう日薬連を通じて行政に提言を行う。
さらに、2025年の通常国会に提出予定の医薬品医療機器等法の改正の動向並びに同改正に伴う政省令等の改正について調査、研究を行い、日薬連を通じて行政に提言を行う。
また、薬事・医療関連等の規制や支援・振興策について、会員会社からの意見・要望を取りまとめ、当局との意見交換等を通じて提言する。 - 会員会社の発展・成長を目指した施策や規制合理化等の積極的な提言
医薬品関連製品のグローバル化に対応した規制・制度合理化に向けた提言、再生医療をはじめとする次世代医療や新たな健康医療製品の上市を迅速化するための規制対応等に対して調査・検討を行い、適宜提言を行う。 - 厚生労働省及びPMDAへの提言
医薬品の承認審査(新規、一変、変更計画の確認)、調査(書面調査、実地調査、GMP適合性調査)、相談業務(対面助言、簡易相談等)、届出業務(治験計画届、軽微変更届、輸出用医薬品製造(輸入)届等)、医薬品医療機器等法関連の輸出入手続及び研究開発の推進等の業務遂行上の問題点について、会員会社から意見・要望を収集し、その改善策について厚生労働省及びPMDAに提言を行う。 - 部会・分科会における活動
- 法令部会
医薬品医療機器等法関連法令及び関連するテーマ・トピックスとして、業態(製造販売業、卸売販売業)管理に関連する事項(法令遵守に関するガイドライン、GDPガイドライン等)、GMPに関連する事項(改正GMP省令、GMP事例集等)、承認申請に関連する事項(一変申請・GMP調査申請に係る照会事項事例検討、不純物管理等)等について調査研究・意見交換を行う。 - 許認可部会
- 第一分科会:
承認書の変更管理(一変・軽微)及びGMP適合性調査など、薬事業務と関連性の高い内容をテーマとしてオンライン通知の検討を行う。さらに、2025年の通常国会に提出予定の医薬品医療機器等法改正の進捗によっては、当分科会に関連する内容を中心に影響度や対応などについての検討を行う。また、講演会等を開催し、医薬関係者として必要な知識・情報についても積極的な収集に努める。 - 第二分科会:
規格及び試験方法欄にかかる記載の合理化、医療用医薬品のGMP適合性調査申請、オンライン提出の留意点に関連した研究テーマを選定し、調査研究を行う。 - 第三分科会:
申請・開発薬事等の分野から、新有効成分医薬品を中心とした薬事戦略及び承認審査・調査並びに日常の開発薬事関連業務において関連性の高いテーマとして、有識者検討会での検討内容に関する調査・検討、CTD M1の記載内容に関する調査・検討を挙げ、薬事的観点から調査研究を行う。 - 製造販売指針分科会:
「医薬品製造販売指針2026」の発刊に向け、最新の規制内容を反映するように追加が必要な法令、通知、事務連絡等を盛り込み、実務を行うにあたってさらに充実したものとなるよう検討・改訂を行う。 - 許認可情報分科会:
PRAISE-NETにて提供される医薬品行政通知データベースの利便性向上と機能強化を図るための提言を行う。また、PRAISE-NETにて、現状、当委員会委員等に提供している許認可担当者向けデータベースの維持・更新のほか課題を検討し、データベースの充実化を図る。許認可情報サマリー作成については、さらなる効率化(外注、生成AI活用)を図る予定である。
- 第一分科会:
- 広告プロモーション部会
医薬品医療機器等法をはじめ、医薬品(医療用・一般用)の広告・プロモーションに係る関係法規(医薬品等適正広告基準、販売情報提供活動ガイドライン、製品情報概要等作成要領、OTC医薬品の適正広告ガイドライン、景品表示法等)や医療用医薬品の販売情報提供活動監視事業等について、事例を中心とした調査研究を行う。また、講演会等を開催し、医薬関係者として必要な知識・情報についても積極的な収集に努める。 - 包装・表示部会
医療用及び一般用医薬品の表示、包装設計、電子添文、特定用符号、インタビューフォーム、等について調査研究を行う。 - 一般薬部会
承認申請、販売業、GMPなど、一般用医薬品特有の課題を中心に、広く日常の業務に関連するテーマとして、一般用医薬品の照会事例、承認基準Q&A等を挙げ、意見交換、情報共有、調査を行う。 - 海外薬事部会
- 欧米グループ:
米国、欧州連合の許認可制度中心に調査研究し、関連するテーマとして、欧米における新薬開発促進に関する制度、米国における工場登録や製品登録の手続きをまとめると共に、意見交換、情報共有を行う。 - アジアグループ:
中国をはじめとするアジア各国の薬事規制等について広く調査研究し、日常の業務に関する意見交換、情報共有を行う。中国チームと中国以外のチームに分かれ、医薬品製造品質管理基準(2010年改訂)の臨床試験用医薬品付録、ASEAN医薬品変更ガイドラインRevision2を活動テーマとして挙げ、検討を行う。
- 欧米グループ:
- 法令部会
- 講習会・講演会の開催
東西合同薬事法規(研究)委員会を東薬工と共催し、厚生労働省医薬局及びPMDAの担当者から最新の薬事動向等について講演が行われ薬事に関する質疑要望に対する回答を得ることにより、薬事業務の一助とする。
また、委員及び部会員の実務に有用であり、部会・分科会活動に関連する講習会、講演会を適宜開催する。
2.技術研究委員会
技術研究委員会では、PMDAの日本薬局方原案検討委員会(以下、原案検討委員会という)に準委員として参画し、日本薬局方原案及び日本薬局方原案作成要領の作成に協力する。適宜、当委員会加盟会社への実態調査や要望調査を行い、行政と業界の間で医薬品の品質評価、並びに規格及び試験方法のあり方や設定の考え方の一致を図る。また、分科会活動、当委員会加盟会社への技術情報の提供及び関係委員会や関係団体との連携・協力を通じ、日本薬局方や製造販売承認申請等の技術的課題の解決に取り組む。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- 日本薬局方改正への協力
原案検討委員会及びそのWGに準委員を派遣し、行政機関に対して要望及び意見具申等を行い、日本薬局方原案作成要領、第二十改正日本薬局方作成基本方針、第十九改正日本薬局方及びその第一追補の作成に協力する。
第十九改正日本薬局方作成基本方針に従い、日本薬局方の整備及び充実、公衆衛生の向上、並びに日本薬局方の国際調和・国際化に貢献する。
当委員会加盟会社が日本薬局方を適切に運用・利用できるように、関係委員会及び関係団体と連携して、技術的及び実務的な課題を解決及び支援する。 - 医薬品添加物規格改正への協力
厚生労働省からの要請のもと、当委員会から医薬品添加物規格検討連絡会議に代表者を派遣し、医薬品添加物規格の改正に協力する。 - 技術情報の提供
当委員会の全体委員会(以下、全体委員会という)において、原案検討委員会、そのWG及び医薬品添加物規格検討連絡会議の検討結果を当委員会加盟会社に報告する。日本薬局方及び医薬品添加物規格改正の最新動向を当委員会加盟会社に提供し、意見交換を行う。
医薬品品質の通知・規制の最新情報又は分析技術の最新動向等に関する講演会を全体委員会と同時に開催し、当委員会加盟会社の実務に直結する有益な技術情報を提供する。
日本薬局方原案作成要領を補完する目的で東薬工と連携して、日本薬局方原案作成要領実務ガイドを作成・発行し、日本薬局方原案作成や試験法開発等に役立てる。 - 日本薬局方への提案及び品質評価の技術的課題への対応
日本薬局方の医薬品の多様化への対応や日本薬局方原案作成の効率化に向けた提案などを関係団体と共に検討する。
日本薬局方及び製造販売承認申請等における医薬品の品質評価の技術的課題について関係団体連携して解決策を模索する。 - 分科会の活動
バイオ医薬品の品質評価方法、規格及び試験方法等を検討する。
全体委員会での分科会活動報告等を通して、当委員会加盟会社と成果を共有する。
3.品質委員会
品質委員会では、医薬品の品質システムの向上を目的として、大阪府をはじめ近畿府県等との連携を図ると共に、日薬連等の業界団体や委員会、会員会社間でのGQP・GMP関連の情報交換を通じて相互啓発に努める。
近年、医薬品の品質システムは国際的整合性の観点から整備・充実が進められており、GQP・GMPに関する省令、通知類及び各種ガイドライン(含む、GDP)等について科学的・論理的な提案・議論が求められている。当委員会は、日薬連を通じて積極的に意見具申に努める。
また、GQP・GMPに係る監視指導やGDPを含めたそれらの運用上の課題を把握し、大阪府並びに日薬連を通じて厚生労働省及びPMDAに要望または意見具申を行い、行政と業界の共通の認識を深めると共に、課題解決に向けて取り組む。
さらに、近年の製造及び品質に関する違反事例や度重なる回収事案により失った国民からの信頼を回復すべく、積極的に業界団体としての対策を計画し、推進するよう努める。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- GQP・GMPに係る監視指導やGDPを含めたそれらの運用上の課題把握及び意見具申
- 次の法改正への要望・意見具申及び改正後の課題への取り組み
- GMP省令改正後の諸対応の推進
- PIC/S GMPガイドライン及びその付属文書(Annex)の改訂
- その他、厚生労働省、大阪府等から示されるGQP・GMP・GDPに関する通知類の課題把握や意見具申
- 近畿圏を中心とした地方行政との連携を推進
- 大阪府との連携
- GQP・GMP・GDPに関連する課題等について、大阪府薬務課との定期的な情報共有及び意見交換を通じて共通理解を図ると共に、課題解決に向けて取り組む。
- 「大阪府薬事審議会医薬品等基準評価検討部会」に参画し、GQP・GMPに関連する課題について意見具申すると共に会員各社へ情報をフィードバックし周知徹底する。
- 近畿府県薬務主管課長会GMPチームとの連携
「近畿府県薬務主管課長会GMPチーム」の活動に協力すると共に、積極的に意見交換を行い、地方行政との連携強化に努める。
- 大阪府との連携
- 重大な品質問題の再発を防止するための業界団体としての施策の立案及び実施
行政との意見交換等も参考にして短期及び中長期の施策を検討し、これらの活動を推進する。 - 実務的課題への対応
品質システム研究部会、ソフト事例研究部会、教育部会の3部会において、実務的課題への対応について検討協議し、解決を図っていく。
2025年度の各部会の研鑽テーマは次のとおりである。
品質システム研究部会:データインテグリティの実践についての掘り下げ
ソフト事例研究部会:供給者・外部委託業者の管理及び製販と製造所の連携
教育部会: GMP・GQPに関する人材育成 - 講演会・説明会等の実施
年2回の全体委員会で委員会活動に関連する最近のトピックスを中心に、日薬連品質委員会及び本委員会の活動状況について報告すると共に、大阪府薬務課はじめ行政からの特別講演を企画する。また、工場見学会等を通じてGQP・GMP関連の情報交換や相互啓発に努める。さらに、協会主催の薬事研修会及び医薬品等総括製造販売責任者講座に協力する。
4.国際ビジネス委員会
国際ビジネス委員会では、事務局と連携し、会員会社の国際ビジネス活動の支援を行うことにより医薬品関連産業のさらなるグローバル展開を推進する。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- 海外の医薬品関連のバリュー・チェーン、研究開発や規制動向についての情報収集・共有の推進
海外のうち、特にアジア諸国(中国、インド、韓国、台湾、ASEAN等)においては、日本企業の事業展開も少しずつ進みつつあるが、収益化の困難さに直面している。市場としても大きく成長してきており、原薬などで重要な製造元であることなどを踏まえ、医薬品関連のバリュー・チェーンに関するセミナー・講演会、ビジネス交流会、現地視察、勉強会、情報共有などを強化する。また、欧米についても、医薬品関連の研究開発や規制動向の把握が重要であり、さらに、アジア諸国や欧米に加え、近年、会員会社の関心が高まっている中東地域も含め、セミナー等により引き続き情報収集・共有に努める。 - 海外バイオクラスター・ベンチャー等との交流
大阪府などの関連自治体や関係団体(バイオコミュニティ関西(BiocK)、神戸医療産業都市推進機構、京都リサーチパーク、千里ライフサイエンス振興財団等)と協力し、海外バイオクラスター・ベンチャー等とのビジネス交流会、講演会等を実施する。また、大阪・関西万博のために来阪する海外からの訪問団との交流会も要望に応じて実施する。 - ステークホルダーと連携した活動の推進
関係国の当局・団体、大使館・在大阪総領事館等、厚生労働省・PMDA、大阪府・大阪市・神戸市などの地方自治体、JETRO、大商・京商・神商、関経連、日薬連・製薬協・GE薬協・OTC薬協等の国際委員会及び現地の日本国大使館、日系企業業界団体との連携を強化し、会議や交流会を通じて医薬品関連産業の国際展開を支援する。 - グローバル人材の育成
医薬品関連分野の海外展開を促進するには、グローバル人材・外国人従業員の育成・確保・定着等が欠かせない。このため、人材育成・確保・定着などの支援に対するニーズを把握し、対応するセミナー、ワークショップを開催するなどして支援を行う。 - 海外への情報発信機能の強化
協会の活動内容等を紹介する英語版のホームページのコンテンツの見直し・充実を図り、2024年に新設した関薬協YouTubeチャンネルも活用して海外への情報発信を強化する。
5.点眼剤研究会
点眼剤研究会では、点眼剤の品質に関わる薬事的、技術的な課題について調査研究及び対策案の作成・提案を行っている。さらに、行政又は製薬団体からの要請に基づく点眼剤に関する課題の調査・検討や提案など、点眼剤の品質向上並びに業界のレベルアップに繋げることを目標に活動を行っている。成果物については、協会ホームページに掲載するなどして、会員会社以外にも広く公開している。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- 点眼剤の適正使用の啓発に関する活動
点眼剤を適正に使用していただくために、現在までに作成してきた「薬剤師向けのハンドブック」及び「患者・一般消費者向けのパンフレット」並びに「小学生を対象とした点眼剤の適正使用に関するポスター」等啓発資料を用いて、点眼剤の適正使用に関する啓発活動を継続する。 - 公定書及び行政通知への対応
日薬連及びOTC薬協からの検討依頼事項(例えば、眼科用剤製造承認基準の見直し、日本薬局方製剤総則・一般試験法及び参考情報の改正、医療事故防止関係、GMP事例集への掲載、通知関連の調査等)について検討する。 - 点眼剤の薬事的及び品質に関わる課題と対策の研究
点眼剤の薬事的及び製造管理・品質管理に関わる課題について、工場見学会、各種勉強会を開催すると共に、研究会委員へのアンケート調査や意見交換により課題の解決に繋げる。また、解釈・用語の統一等を図ると共に、その対策についても検討することにより、知識・技術の学習支援を行う。 - 東薬工点眼剤研究会との連携
点眼剤業界としての意見を集約して行政及び業界団体等への提案活動を迅速に行うために、東薬工点眼剤研究会と連携し、東西合同の調査・研究成果報告会や意見交換会を実施する。また、医薬品・関連製造工場の見学会等を含む研修会や勉強会を開催し、東西研究会委員の医薬品関連全般の知識・技術の学習支援と品質向上に繋がる意見交換を行う。
6.知的財産研究会
知的財産研究会では、1)特許・特許情報・商標の分野ごとに部会を設置し、医薬分野のみならず近年製薬企業が取り組むヘルスケアに関連する特許・商標の審査・審判等における知財関連制度の諸問題や知財情報の調査・検索等の実務における課題に対し、各部会で研究テーマを決めて情報収集や実務的な検討を行う。また、2)東薬工知的財産研究会と連携して特許庁その他の関係機関との意見交換を行うことにより、得られた情報や検討結果などの成果を会員会社に発信することで、会員各社の知的財産活動を支援する。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- 特許部会
国内外の特許制度に関する諸問題を検討する。
国内については、特許法の改正や審査基準改訂後の動向に留意し、適時、特許庁の審査・審判の実務面を中心に情報調査・検討に努め、成果を会員会社に提供する。また、会員各社の意見を考慮しながら、必要に応じて東薬工知的財産研究会と連携し、特許庁その他の行政機関に要望及び意見具申等を行う。各国の特許法に関係する判例や医薬・ヘルスケア関連の情報収集に努め、それらの調査・解析を行い、製薬業界が近年直面している課題を抽出し、その対応を提言する。 - 特許情報部会
特許情報部会は参加を希望する会員会社が少なかったことから休会とする。 - 商標部会
商標部会は参加を希望する会員会社が少なかったことから休会とする。
7.くすり相談研究会
くすり相談研究会では、医師・薬剤師などの医療関係者をはじめ、一般消費者、患者からの問い合わせに応える顧客対応部署に係る諸問題を取り扱っている。多種多様な問い合わせニーズに応えるため、自社製品に関する製品知識だけでなく、電話応対スキルの向上、コールセンター運営ノウハウの習得、その他幅広い周辺知識の習得に努めており、各種勉強会、研修会を開催している。
また、社会貢献活動の一環として大阪市すこやかパートナーに登録し活動を行っている。2024年度から大阪市平野区の自治会館に出向き一般消費者に対し、「おくすりの飲み方教室」と題した医薬品の適正使用を目的とした出張講座を開催しており、2025年度も継続開催する。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- 全体研究会及び部会活動
全体研究会は、PMDAが主催する「くすり相談事業担当責任者連絡会議」や日薬連安全性委員会くすり相談部会に当研究会から代表者が出席し、入手した情報を委員にフィードバックすることにより相互理解の向上に努める。
下部組織として情報検討部会と事例検討部会を有し、月例定例会を通じて委員相互の自己研鑽、相互研鑽に努める。
情報検討部会では、各種勉強会や研修会の企画・立案・運営を通じて自己研鑽に励むと共に、研究会活動が魅力あるものとの評価を得られるよう努める。
事例検討部会では、相談事例の検討を通じてコミュニケーションスキルの向上を図ると共に、その検討結果を会員会社にフィードバックし、各社教育用教材として利用できるよう努める。 - 講演会・研修会等の開催
以下のイベントを引き続き開催し、幅広く知識習得に努めると共に、委員のスキル向上に貢献する。
- くすり相談フォーラム
- 問い合わせ対応スキルアップ研修会
- 施設見学会
- 幅広い知識を習得するための各種勉強会の開催
委員のニーズを把握し、関心の高いテーマについて適宜勉強会を開催して知見を得るよう努める。 - 関連団体との連携
日薬連、東薬工、製薬協と共通する課題(顧客対応など)への対応について連携を検討する。
8.医薬品安全性研究会
医薬品安全性研究会では、医薬品の安全対策について、行政、日薬連等が主催する検討会・事業等に参画し、最新の情報の収集に努めると共に、適時・適切に会員会社へ情報をフィードバックし、通知等の情報を周知徹底し、各社の安全対策を支援する。また、常任研究会を中心に医薬品の安全対策に係る新たな課題について意見交換・検討し、必要に応じて行政、日薬連等への提案等を行う。さらに、啓発事業として講習会、研修会を企画・実施すると共に、情報部会では実務担当者の副作用評価能力向上等の啓発を行い、迅速かつ的確な製造販売後安全対策が講じられるよう会員会社を支援する。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- 新たな製造販売後安全対策への対応
2025年度に予定されている医薬品医療機器等法等の改正や新たな安全対策の動きについて、行政、日薬連(日薬連安全性委員会に参画)等を通じて適時情報収集に努め、会員各社にフィードバックし、各社の製造販売後安全対策の活動を支援すると共に、必要に応じて日薬連等への提案等を行う。 - 製造販売業者の遵守事項(安全性)への対応
GVPに関する都道府県の立入調査及びPMDAによるGPSP適合性調査の状況等、関連情報をタイムリーに収集・提供して会員会社が円滑に対応できるよう支援する。 - 医薬品情報提供システム等への対応
日薬連情報提供システムプロジェクトに参画し、PMDAの「医薬品・医療機器情報提供ホームページ」に関して意見具申すると共に、会員各社に情報をフィードバックし周知徹底する。 - 地方薬事行政への対応
大阪府薬事審議会の医薬品等基準評価検討部会及び医薬品適正販売対策部会に参画し、意見具申すると共に会員各社へ情報をフィードバックし周知徹底する。 - 医薬品の安全対策に関する啓発
外部講師による医薬品の安全性に関する講習会の企画・実施や薬事研修会及び医薬品等総括製造販売責任者講座の講師実施により、医薬品の安全対策の重要性について啓発する。また、情報部会(毎月定期開催)では、グループワーク等による重篤な副作用症例、研究報告及び措置報告の検討を通じて、実務担当者の安全管理情報の評価能力の向上並びに行政への適正な報告様式の作成等、遺漏のない対処ができるように支援する。加えて、公表されたRMPを題材に、当該医薬品のRMPの構成及び安全性検討事項等のエビデンスを検証し、RMPの理解をより深めるよう支援する。さらに、常任委員による話題提供並びに安全管理業務における課題や関連通知類の理解の共有等を通じて、部会員の対応能力の向上を図ると共に、会員各社のGVP・GPSP体制の強化を支援する。
なお、情報部会での重篤な副作用症例、研究報告及び措置報告並びにRMPの検討資料を成果物として当研究会の加盟会社に公表する。
9.教育研修研究会
教育研修研究会では、MRの導入教育及び継続教育の質の向上を目指して、会員会社の教育研修内容の充実・強化を目的に、効果的なMR教育研修の支援を実施する。また、2026年度MR認定制度改定に向け、MR認定センターの各種委員会に対して、会員会社の要望事項が反映できるよう努める。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- 実務教育認定基準のパイロット運用
2026年度からのMR認定制度改定案では、基礎教育と実務教育を切り離した“2階建て”と称する生涯教育制度が提案されている。
- 基礎教育:基礎知識の習得・維持を目的に個人が実施する学習(1階部分)であり、科目は、医薬品情報、疾病と治療、MR総論である。基礎教育でCBT試験を受験し合格の証を取得する。また、MR認定センターが提供するプログラムで所定の個人学習を行う。
- 実務教育:企業が責任をもって実施する教育(2階部分)であり、科目は、倫理、安全管理、技能、企業が必要とするその他の科目である。実務教育は導入教育と継続教育で構成されている。導入教育は、教育研修、成果確認、終了報告を経て修了認定を取得する。継続教育は企業が行う教育研修である。 実務教育には新たに実務教育認定基準が策定され、実務教育認定基準に基づくOJTが2026年度から正式に導入される。2025年度は、その準備としてパイロット運用を行うため、教育研修並びに成果確認方法などの実務教育認定基準の運用に関する情報共有を図る。
- MR教育担当者講座
MR教育担当者講座は、MR認定制度やMRテキストと関連するカリキュラムを設定し、会員会社の教育研修を支援する。講師は、当研究会の加盟会社の中から研修内容の精通者を選出すると共に、科目によっては外部講師に依頼するなどして、最新情報を提供する。また、本講座の開催案内やポスターを協会ホームページや機関誌「会報」に掲載して広報活動に努める。 - MR認定センター関連の活動
MR認定センターと連携を図り、以下の活動を行う。- MR認定センター教育研修委員会に当研究会から代表者を派遣し、定期的に開催される教育研修委員会に出席し、適切な情報の収集に努める。
- MRフォーラム、教育研修推進者会議、教育研修システム認定講習会等で最新情報を収集し、会員会社の教育研修に反映させる。
10.治験推進研究会
治験推進研究会では、会員各社が抱える治験に関する事例を持ち寄り、活発な意見交換を行うことによって、治験現場の実態に即した具体的な解決策を見出し、それを会員各社にフィードバックすることを目的に活動を行っている。また、この意見交換を通じて、会員各社が共有できる事項を成果物としてまとめている。
2025年度に重点的に取り組むべき事項は、次のとおりである。
- 分科会活動の推進
当研究会の下部組織である治験部会は、分科会を設置して治験に関する様々なテーマについて種々検討を行っている。2025年度は2024年度に引き続き以下4テーマについて、それぞれの分科会において分科会員がお互いにGCP関連等の最新情報や知識・経験を共有し相互研鑽に努める。こうした活動を通じて、会員会社における効率的かつ効果的な治験の実施を支援する。
- テーマ1:治験における品質マネジメント計画書・報告書作成の手引き
- テーマ2:将来のGCP Renovationを見据えた検討
- テーマ3:メディカルアフェアーズの可能性を広げる
- テーマ4:ICH M13Aガイドライン「即放性経口固形製剤の生物学的同等性」に対応する後発医薬品(ジェネリック医薬品)の生物学的同等性試験の実施手法に関する検討
- 協会事業の支援活動
協会が年間カリキュラムにより開催している薬事研修会には、例年どおり、GCP関連テーマの講師を務め、会員会社における実務担当者の知識向上に貢献することとする。 - 関係機関等との連携
厚生労働省、PMDA、大阪府、治験ネットおおさか推進会議、日本QA研究会、大阪府医師会等と連携を図り、関係機関から入手した有益情報の発信に努める。その他、関係機関等からの要請に応じて、各種催し物等の広報を行うなどの連携活動に努める。
入会のご案内
会員向け情報
会員会社の方のみ閲覧可能。
(要 PRAISE-NETログイン)
関西医薬品協会 〒541-0044大阪市中央区伏見町2-4-6
Tel:06-6231-9191 / Fax:06-6231-9195 / Mail:info@kpia.jp
- 営業・セールス等を目的としたお電話・Fax・お問合わせ等はご遠慮ください。
- 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。